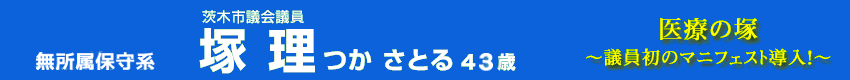
■塚 理の4つの茨木市未来創成ビジョン2021(2021年1月15日追記【完全版】) |
|
◎地域第一!政策中心!政治の「見える化、わかる化、いかす化」 始めます!! 1、お祖父さん、お祖母さん、お父さん、お母さん、子どもたち。 みんなが笑顔の街づくり。 2、みんながわかって納得の街づくり。 3、いつも安心・安全の街づくり。 4、みんなが住みたい、住んでよかった街づくり。 |
■(医療)地域医療再生!健康都市いばらきへ!!地域で医療を守り、育てます。・医療体制の充実。 ・予防医療、予防介護への取り組み強化。 ・心のケア、認知症対策の充実。 ・持続可能な地域医療を創り、安心な医療体制の構築。 ・医療と福祉の連携強化。 ・大学等との連携による医療従事者の確保。 ・各医療機関への連携支援。 |
■(福祉)地域で一緒に助け合い、生活できる場所を創ります。・茨木版地域包括ケアシステムの構築。 ・山間及び丘陵地域や郊外地域での高齢者等の移動支援への取り組み。 ・各医療機関へのアクセスの工夫。 ・介護や保育に携わる人材の確保及び処遇改善。 ・高齢者、障がい者の雇用や居住対策。 ・障がいについての正しい理解をより普及させます。 |
■(子育て・教育)子どもたちに優しい街は高齢者にも優しい街。将来の納税者への先行投資として総合的政策をおこないます。・茨木版ネウボラの構築。 ・保育園待機児童の解消。 ・産前産後や幼少期への手厚い支援をおこないます。 ・障がいのある子どもへの支援の充実。 ・子どもたちのために行政の風通りをよくします。 ・CSRでの子育て支援企業に対する優遇措置。 |
■(街づくり)地域格差ではなく地域の特徴を活かします。・都市縮小時代に向けてのコンパクトシティの充実。 ・JR茨木駅、阪急茨木市駅前、阪急総持寺駅前の再整備事業や市中心部整備事業への取り組み。 ・新しい企業誘致対策。 ・企業の社会的責任(CSR)を用いた民間との連携事業。 ・市内大学と市内企業とのインターンによる雇用創出マッチングシステム。 ・市内企業への支援拡大。 |
■(行政運営)行政も経営だ!!攻めの行政経営をおこない、子供にツケをまわさない行政運営をおこないます。歳出削減には限界があり、歳入を増やす政策をさらに実施します。・行政マーケティング制度の実施。 ・行政をもっと見える化へ。 ・より魅力のある人財の発掘と登用をおこないます。 ・部長マニフェストの導入。 ・公益通報制度の確立。 ・電子自治体の更なる推進。 |
■(環境)子どもたちへの贈り物~環境未来都市を目指して~・行動する環境教育。 ・「もったいない」から「得する」事業。 |
■(議会改革)行政チェック機関から政策提案集団へ・考える議会から行動する議会へ。 ・見せる議会から魅せる議会へ。 |
■(市民活動)住民主体の市民活動と住民参画の街づくりを実践します。・防災、防犯に対しての地域対策。 ・高校生や大学生からの住民参画。 ・遊休農地、生産緑地、竹林、山林を活用し、農と教育、福祉との協働で都市近郊農業や里山の保全・活性化を図ります。又、鳥獣対策にも力を入れます。 ・都市近郊農業の特性を活かした事業。 ・市民活動センターの充実とコミュ二ティビジネス支援 |
|
新しい項目だけでなく、前回から取り組み中の項目も実現を目指してまいります!! *茨木市未来創成ビジョンの財源は私の研究の中から生み出され、茨木市で軽減される社会保障の負担額を中心に考えています。又、ソーシャルキャピタルやCSR、クラウドファウンディング、ソーシャルインパクトボンドの活用など、できるだけお金がかからないような施策を多く考えています。 |
| ←HOMEへ戻る |